『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない
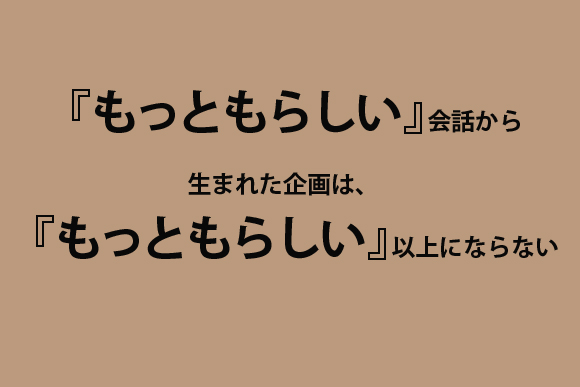
今日は、私のポリシーについて書きたいと思います。
私のポリシーの一つに、タイトルにある「『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない」というのがあります。
では、『もっともらしい』会話とは、どういうことでしょうか。
まず、『もっともらしい』の国語辞書的な意味は、「(本当はよく考えてもいないのに)いかにももっともだというふうに説くこと」です。では、『もっとも』の意味は何かというと、「何よりも一番」とか、「道理にかなっていること」です。つまり、『もっともらしい』会話というのは、「あることについて、本当はよく考えてもいないのに、いかにも道理にかなっていて、一番良いと語り合っている会話」のことです。
どういうことか、社内広報のシーンでの「もっともらしい会話」の具体例を挙げてみました。たとえば、、、
「この企画の目的は、部門間のコミュニケーションを活性化することです」とか、
「新たな中計の狙いを訴求して、社内のベクトルを合わせることが必要です」など。
いえ、このような会話が悪いわけではありません。本当によく考えたかどうかが、問題なのです。たとえば、「部門間のコミュニケーションを活性化する」と言いながら、どうなった状態が活性化した状態なのかまでは考えていないとします。そうすると、「部門間のコミュニケーションを活性化する」という台詞はいかにも道理にかなっていて、一番良いというニュアンスで語られていますが、実は形の上での話でしかないことになります。
ところが、私たちは、この「もっともらしいこと」が大好きなんですね。
なぜか?
理由は単純。安心したいからです。道理にかなっているように見える言葉で語り合うことで、安心が得られます。自分たちは間違っていない方向に足を踏み出しているように思えるからです。
でも、私はこう考えます。安心を得たい気持ちを少し脇に置いておいて、「それはどういうこと?」「それはどういうこと?」「それはどういうこと?」を繰り返して問い続けると、「もっともらしいこと」から脱出できる、と。頭で汗をかいた分、ちゃんと自分の血肉になった言葉が生まれてきます。
でも、社会では「もっともらしい」ままスルーしてしまう風潮があるのも事実。たとえば、30分の議論で出て来たコンセプトでも、「道理にかなっている」と思って、ヨシとすることはよくあるのではないでしょうか。もちろん、30分で考えたコンセプトでも、瞬間的なひらめきから素晴らしいコンセプトにたどり着く場合はあります。でも、確率論的に言えば、そんなことはななかなか起きません。
複数の人が参画しているプロジェクトで、各自が思考を深め、レベルを合わせようとすると、私の経験では平均4時間ぐらいはかかります。2時間で実現できないとは言いませんが、参加者が置いてけぼりにならないためには、そのくらいの時間が必要です。反対に、4時間かければ深まるという法則はありません。もっとかかる場合もあります。
私たちは、今その場で起きていることが「もっともらしい」レベルかどうかについて、もう少しアンテナを張ってもいいのではないでしょうか。そのチェック方法の一つは、「つまり、それはどういうこと?」を問い、自分の言葉で語れるかどうかです。現実世界では、4時間も割けないまま、結論を出さなければならないことが起きます。でも、「もっともらしい」レベルかどうかへのアンテナが立っていると、今、その場にいる人の理解のレベルがわかるようになります。そうすると、「ここはまだ深い理解には到達できていないけれど、それなりに進めよう」という話ができます。それだけでも、置いてけぼり感がなくなると思うのですが、みなさんはどう思いますか?
『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない。会話の状況を察知し、セルフアラートを出せるような人が増えると、もっとアウトプットの質や生産性が高まるのではないかと思うのは私だけでしょうか。



