『ココロのミステリー』カテゴリの記事
継続は力なり? 再起も力なり!

今年最後のメルマガをお送りします。
みなさんは、この1年、どんな年でしたか?
どんな人にとっても、良いこともあれば、
私も同じです。
ことメルマガに関しては、決めた頻度で配信できず、
ちょっと情けない年になってしまいました。
毎週1回(年50回弱)のはずが、
このメルマガは2013年7月4日から始めて、満12年超。
2022年頃から定期配信がぐらついてきました。
いったいなぜそうなったのか、正直に書いてみようと思います。
事情や心情には主に次のようなことがありました。
(1)どうにもならないほど忙しく、
(2)(1)番ほどの状況ではないけれど、少し忙しい時に、
「ま、いいか」と優先順位を下げてしまい、
(1)番はそんなに頻繁にあるわけではないので、問題は(2)
いっしょにメルマガを書いている阿部も、
優先順位を下げてしまう局面があったり、ネタ切れ感があったり、
こんな話は読んでもつまらないだろうという気持ちになり、
ブレーキがかかったこともあったようです。
実際、原稿作成というのは、書くことが決まってしまえば、
そこからは意外にスムーズに進みます。
メルマガで一番悩むのは何を書くかを決めるまで、です。
ですが、それがなかなか決まらないことがあります。
共通するのは、忙しくて、観察・
そうすると、なかなか書きたいことが決まりません。
ずっと「継続は力なり」と思ってやってきたのですが、
継続が崩れてきた今、「再起も力なり」なのだろうと思います。
私は、人が物事を継続するためには、
優先順位を下げないだけの「目的意識」
これは、
で、大抵の場合、もちろん最初はそこを明確にして始めます。
なのですが、時間とともに目的意識は遠のきます。
当社のメルマガの配信頻度が下がった理由も、
そのようなことが起きたのだと思います。
というわけで、来年はリセットして臨みます。
「ご期待ください」と宣言するのも憚られますが、
有言実行に追い込む方が対策としては有効な気がしますので、
来年はご期待ください! あ~あ 言っちゃった~
反省文のようなメルマガで終わっては立つ瀬がありません。
年末年始は、多くの人が目標を立てる時期でもあるので、
といっても、
当社では、毎週1回、
シェアといえば聞こえがいいのですが、これは I さんが発表した内容のパクリです(笑)
ーーーー【継続のコツ】ーーーー
【その1】毎日やる
頻度は毎日がベスト。やってもいい/
【その2】1分でもいいからやる
「やった」という成功体験は1分で可能。
【その3】いつやるかを決める
暇な時間は一生できないから、時間ができたらやるはNG。「○○
【その4】小さな行動を2つセットでやる
普段やってることと新しくはじめることをセットにする(例:
【その5】どうしてもやりたくないときは、やるふりをする
たとえば、ジムに行くために着替えて玄関までは、行ってみる。
【さらにオマケ】思うようにいかないときも自己否定はしない
自己否定しさなすぎて、
ーーーーーーーーーーーーーーー
なんでもかんでも継続すれば良いわけではありませんが、
たとえ小さなことであっても、決めたことを継続すると、
自分の自信になりますし、
周囲がそれを認知して、一目置いてくれるようになります。
つまり、その結果、自分のブランディングに役立ちます。
自分のことは棚に上げて言います。ぜひ試してみてください!笑
私個人は、
生かしていきたいと思います。
さて、2025年、今年も大変お世話になりました。
来年も、どうぞよろしくお願いします。
2026年が幸福に溢れた1年になりますように! 良いお年を!
心の「モード」を変えてみる

先日、ブルージェイズとのワールドシリーズ(7回戦制)
1勝1敗で本拠地に戻った大谷選手が、
「終わったことは切り替えて、
これを聞いた時、「さすが!
この言葉に触発されて、
さて、、、
ネガティブな出来事が生じた時に、
その出来事に気持ちを引きずられないことが大切だと多くの人は知
だから、大谷選手のように、「気持ちを切り替えよう」
ほかにも気持ちの切り替えの例えとしてよく聞く言葉としては、
「やる気スイッチを入れる」というのもありますね。
この気持ちの切り替えやマインドのコントロール、
これは特にスポーツをやっているときに、
私にとって、ゴルフなどは最たる物です。
それが、なかなかできないのですが。
で、
これはこれで大事だと思うのですが、
今回はもう少し広い意味で、自分の意識のコントロールについて、
考えてみようと思います。
私はそれを意識の「モードチェンジ」と呼んでいます。
皆さんは、今はこういうアンテナを立てた方がいいな、
ここで私が言うアンテナとは、自分の意識のアンテナです。
何かを感じ取るアンテナと言ってもいいかもしれません。
人には野生的・本能的なアンテナがあるのに、
自分を含め、
今から10年ぐらい前のことです。
いわゆる「リトリート」
たとえば誰にでもワクワクすることがありますよね。
でも、アンテナが錆びついていると、そのワクワクに気づけない。
本当は、
そこに鈍感でいるのは嫌だなと思ったことを覚えています。
そうこうするうちに、
だとしたら、それらは自分でコントロールできる方がいいな、
いえ、
意識するとイメージが明確になります。
たとえば、、、
ゆっくり、サクサクというスピードに関するアンテナ、
ズームイン、ズームアウトという視界の広さに関するアンテナ、
ココロの状態、カラダの状態に敏感になるアンテナ、
しっとり、ノリノリなど、今、
そして、もちろん昨日は昨日、
ほかにもたくさんあることでしょう。
私のイメージとしては、
コントロールパネルもあって、オン・オフできる、
まさに、「やる気スイッチ」
つまり、
そんなイメージです。
そうすると、どう思うようになるかというと、
今は、焦る気持ちを抑えて、敢えてゆっくりモードでやろう、
この状況は、広角レンズで俯瞰して見た方がいいな、とか、
今日は弾けモードでいっちゃえ、というように選択的になります。
しかも、意識と無意識の中間で、
私は、この「アンテナとコントロールパネル」
押し売りはしないまでも、
特に若い方に対して、です。
それは、ゆっくり、
とかく仕事は速い方が良いし、
でも、敢えてゆっくりモードでやってみる。
これは、ホントおすすめです。理由? 秘密です笑
強いていえば、同じ動画でも、
まあ、騙されたと思って、やってみてください。
まもなく11月です。
秋の終わりを満喫したいものですね。
言いにくいことを伝える

Xを見ていたら、タイムラインに中野信子さんの著書「
広告らしきものが流れて来て、
私は、別に「毒の吐き方」には興味はありませんでしたが、
「脳科学と京都人に学ぶ『言いにくいことを賢く伝える』技術」
「エレガントに伝える」「京都人」に興味を持ち、
いえ、読んだのは本書ではなく、記事の方です。
発売は、2023年5月なので、
読者はどこに惹かれて読むのだろう?
もし「毒の吐き方」だとしたら、いやな世の中ですね。
でも、「言いにくいことを伝える」は、
私にも、月に何度かは言いにくいことを伝えるシーンがあります。
プライベートと仕事の両方を合わせてです。
そこで、今回は、人はなぜ「言いにくいことを伝える」
どうしたら少しでも悩まなくて済むのか、
我が身を振り返りながら考えてみたいと思います。
人が「言いにくいことを伝える」には、
大別すると、次の2つではないでしょうか。
第一は、そもそも思っていることを伝えるべきなのかどうか。
第二は、伝えた方が良いと思っても、
でも、自分が当事者で悩んでいるときは、
ちなみに私自身は、伝えるべきかどうかについては、
大抵は野生的本能で「伝えるべき」「伝える必要はない」
でも、伝えるべき理由については、結構考えます。
さて、まず葛藤の第一。
思っていることを伝えるべきかどうかで、
原因はいろいろ考えられます。
【結果が不安】それを言って、相手が分かってくれるかどうか、
→理解されないと、相手の気分を害するだけで、
【目的が不安】こんなことを思う自分は、
→伝える目的はエゴなのか、関係維持のためなのか、何なのか、
【感情と理性の線引き(目的の揺れ)】
→
感情が混じってしまい、考えが整理できない。
ほかにもあるかもしれません。
ここでは私の経験から自分の心理を分析して整理してみましたが、
実際に何かに直面したときに、
どうでしょう? 案外難しいような気がします。
第二に、伝えた方が良いと思ってもどう伝えたらいいかで、
これについて、私は、
が、それを含め、次の2つに注目したいと思います。
1つは、【目的の不明瞭さ】からくるものです。
そりゃそうですよね、何のために伝えるのかによって、
伝えるときのスタンスが変わり、
そもそもなぜ自分は伝えたいのかで揺れているにも関わらず、
どう伝えようと考え出すから、分からなくなるのは当然です。
もう1つの原因は、仮に目的が明瞭だったとしても、
【伝えるスタンス】が定まらないと、
仮にですよ、
コテンパンにやり込めたいというスタンスでいくのか、
分かってくれれば良いというスタンスでいくのかによって、
伝え方は大きく変わります。
一刀両断には言えませんが、多くの場合、
どう伝えたら良いか、悩むのだと思います。
さて、私自身は「言いにくいことを伝える」
伝えるというのは、とても面倒で、エネルギーのいる行為です。
ということは、関係を維持したり、向上させたり、
何らかの共通目的を達成したりするというような、
そこにエネルギーを使うことは人生の無駄遣いに思えます。
どうでもいいことのために、
もっといえば、どうでもいいことであるなら、
反対に、目的を関係の維持・向上だと思ったら、
相手をやり込める必要はないと分かります。
思いを伝え合うときに私が大切にしたいのは、
まず自分の発言に責任を持つことです。
そのためには、自分の感じたことを感じたこととしていうこと。
感じたことは私の主観であって、客観的事実ではないのですから、
「あなたはこうだ」とあたかも事実であるような評価・
自分の発言が主観であることを表現するには、
あなたのここが良くないではなく、自分はこう感じたよ、と。
そのスタンスを持つことで、
すると、自分の気持ちもラクになります。
そして、相手も人間ですから、自覚していることもあれば、
たまたまその日の気分で起きてしまったこともある。
感じた私の心だって、日々揺れているはずです。
そして、お互いを尊重する気持ちが根底にあれば、
言いにくいことを言ったあとも、お互いに「
「そういうこともあるよね」と受け入れられる気がします。
便利なことわざ「物は考えよう」

当社では、現在採用活動を行っています。
そのことで、先日、
自己客観視ができて素直であることは、
重視していることのひとつだと答えたところ、
「自己客観視か...。私は自己肯定感が高すぎて、全然ダメ」。
要するに自分のことを否定的に見ることができない、
ということのようです。
本来、自己肯定感と自己客観視は両立するものだと思いますが、
この友人は、
と捉えているようでした。
ところで、最近は自己啓発系のコンテンツの影響からか、
「自己肯定感が高い/低い」とか
「承認欲求が強い/弱い」など、
自己認識して言語化するような風潮が強まっているように感じます
自己肯定感で言えば、
まあ、もちろん、そうなのでしょうが、
あまり、それに振り回されるのはよくないとも思います。
というのは、自己開発のための知識を増やした結果が、
必ずしも良いものになるとは限らないからです。
言葉にはプラスのパワーもあれば、
マイナスのパワーもあるため、
たとえば、「自己肯定感が低い」と自認してしまうと場合、
その言葉に縛られて自己像が作られがちです。
そんな必要はないのに、
ですので、
少々の違和感があります。
ネガティブな自己認識はそんなに悪いことでしょうか。
たとえば、「自分はダメな人間だな」と思ったとして、
そんな自分をどう捉えるかは考えようです。
ある一面から見たら、謙虚さの現れだし、
また別の一面から見たら、
こうありたいと願うのは、まさに美意識そのものですから。
どんなものにも表と裏の二面性があります。
そのどちらに目を向けるのかは、自分で決定できます。
物は考えよう。
なんと便利なことわざではありませんか!
いつにも増して暑い夏です。
熱中症に気をつけて、健やかにお過ごしください。
出会いたい人と出会うために
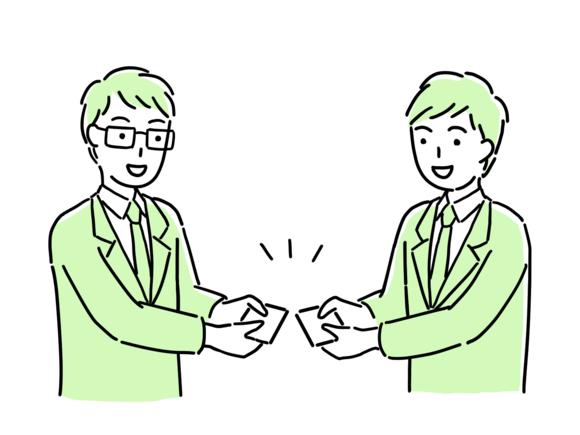
何をするかよりも、誰とするかだ...という表現、
一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
けれど組織では、仕事は上からのアサインありきだから、
誰とするかなど、自分の意思で決まるものではない。
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
一方で、やりたいことを見つけてそれに打ち込む人生が良い...
多少弱まってきた気がしますが、
そして、そのような考え方は、「やりたいことが見つからない」と
思っている人たちに、
私自身がどうかというと、「人生は波乗り」
「やりたいことをやる」は、それはまあ幸せかもしれないけれど、
一度コレと決めたら変えられないような呪縛になりそうだ、と。
なぜなら、人間のやりたいことなんて、どんどん変わるからです。
だから、やりたいことが何かを見定めて、
実は強そうでいて、案外脆いのではないかと思ったりします。
人生は波乗りで良いと思う私が何を得たいと思ってきたかというと
1.やりたくないことをしない。
2.出会いたい人と出会えるようにする。
3.物事をより良くすることを楽しみたい。
ざっとこんな感じです。
やりたいことありきで人生を考えるというよりも、
この3つが満たされたら、十分幸せだという考え方です。
(もちろん、やりたいこともやっていますが、
仕事では、「インターナル・コミュニケーション」という領域で
専門サービスの提供に努めていますが、
私の中では、
そして、出会いたい人はどんな人かというと、
物事をより良くしたいと思っている面白い人たちです。
やりたくないことが何かというと、
物事をより良くしようと思っていない人と仕事をすることです。
さて、上の3項目の中で、一番難しいのが、
2番の「出会いたい人と出会えるようにする」かもしれません。
仕事に置き換えると、「何をするかではなく、誰と働くか」。
では、どうしたら出会いたい人と出会えるのでしょうか。
「出会えるようにする」などということが、
私は、ブランディングという考え方に立ち、実践すれば、
個人であっても実現可能なことだと思っています。
たとえば私自身を例に挙げると、
出会いたい方たちからご連絡をいただく機会が増えたと思います。
では、パーソナルブランディングという観点から考えたときに、
どうすると出会いたい人、
私は、そのコツは、第一に「意思表示」
たとえば...
・私は、こういうことを大切にしている人間です。
・私は、こういうことに関心のある人間です。
・私は、こういう人と仕事をしたい人間です。
ただの自己紹介ではなく、自分の意思を示すこと。
それを、十人に話すと、一人ぐらいが覚えてくれて、
求めることに近い話をもたらしてくれる可能性が高まります。
別に、そのように計算して生きてきたわけではありませんが、
意思表示には力があるなと感じています。
パーソナルブランディングなどと難しいことを言わずとも、
自分という人間について、相手にどう覚えてもらうか。
それによって、出会いが広がり、人生が広がるのだろうな...。
信じる者は救われますよ笑
「意が伝わる」で大切なのは「幹」
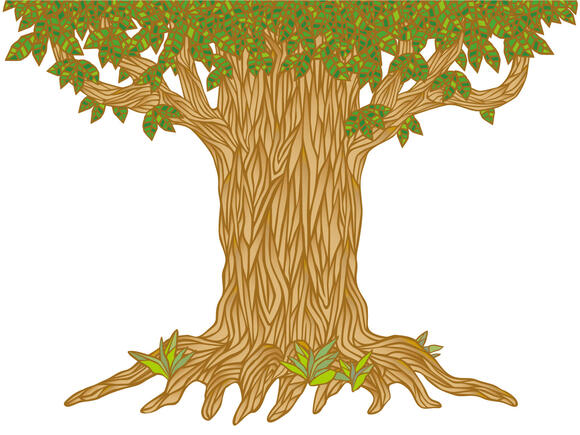
今日は、最近起きた3つの出来事を通じて思ったこと、
つまり表題にあるように、
ということについて私の脳内ぐるぐるをシェアさせてください。
自分のぐるぐるをそのまま吐き出すなーとも思いますが、
1つめの出来事です。
先週、私どものあるお客様企業の新社長になる方に
インタビューをさせていただく機会がありました。
その中で外部に自社の価値を伝えることがいかに大切かという話題
しかも、ただ説明すればいいわけではなく、
相手にとって「面白いか」「分かりやすいか」が重要で、
それが満たせると物事は自然と広まっていく。
インタビューの主題ではありませんでしたが、
また、2つめ、先週社内ではこのようなことがありました。
私が講師役となり「伝える技術」を学ぶ、
「テーマとは何か」を学ぶ課程では、
主題を端的に語ることの大切さを学んでもらうのですが、
「~について取り上げる」の「~」
簡単そうで簡単ではありません。
たとえば、「ABCプロジェクトについて」
「ABCプロジェクトの~について」
何に焦点を当てるかを言葉で表すとどうなるか。
やってみると、誰もが言葉を絞れずに悩むわけです。
「メッセージ」を言語化する場合にも同様なことが起きるので、
伝える人は、
この勉強会からの私の気づきは、
自分の考えの根幹を明確にしてから、相手に伝えるには、
自分の言葉を絞る必要があるわけですが、
それには理屈だけでは解決できず、
スポーツのようなトレーニングが必要なんだろうな、
さて、3つめ、最後のエピソードになります。
「伝わる」について考えさせられる出来事があった今週、
今度はなぜか不意に心が動いて、
なんと何十年かぶりに英語の学習教材を買いました。
基本はたった81文だというコンセプトで書かれた
「Simple English Magic 81」(著:酒井一郎)という本です。
きっかけは、この本を読むよりも前から、
若い時よりも英語が聞こえるようになっている気がする、
なぜだろうと考えてみると、
大体の大筋は何かと思って聞くと、想像力も手伝って、
こんなことを言っていると分かる。
昔は、聞き取れなかった単語が気になって、
私の自己分析を裏づけるかのように、
"I play baseball in the park next to the hospital."という一文を聞いた人の多くは、
"next to"に意識が向いてしまい、それよりも重要な"I play baseball"が
二の次になってしまう。
文意としては、そのようなことが紹介されていたのです。
つまり、人間が何かを理解したり、
幹が先であり、枝葉は後であるべきだということでしょう。
そしてまた、学習にも幹と枝葉があり、
滅多に使いもしないイディオムは枝葉、
幹は中学レベルで十分だということから、
つまり、相手に「意が伝わる」ようにするために大切なのは幹、
私が、テーマやメッセージを端的に絞れと教えているのも、
幹が先であり、枝葉は後だと思うからです。
3つの出来事を通じて、「伝える」「伝わる」
お付き合いいただき、ありがとうございました。
さて、当社、2週間後には通い慣れた表参道を離れ、大門/
引越し準備、大変でーす!
皆さんも期末でお忙しい方も多いと思いますが、
前年比7%増の自己成長って?

最近、ふとこんなことを考えました。
「年齢が上がると成長しにくい」は本当か?とか、
私自身の今の成長を数字で表したら、どうなるのだろう?と。
目標管理の世界では、目標はメジャラブル(測れるもの)
しばしば言われますが、目標と成長は別物です。
自分が対前年比で何パーセント成長したかなどと考えたり、
10年後には何倍に成長していたいなど、
数字で自分の成長を考える人は少ないのではないでしょうか。
また、いざイメージしてみようと思っても、
基準もないので、イメージできないという人が大半だと思います。
私自身は何歳になっても人は成長できると信じていますが、
キャリアが上がれば、新人の時のように
急成長を実感することはなくなるのが普通です。
というわけで、今日は「成長」を数字でイメージする、
チャレンジしてみたいと思います。
実験です笑、お付き合いください。
そこで、まず資産形成や社会経済を例に考えてみました。
たとえば、資産運用だとどうでしょう?
100万円を年利5%で運用すると、5年後に1.
年利6%で運用した場合は、7年後に1.5倍、10年後に1.
年利7%で運用すれば5年で1.4倍、
「今どき7%?」と思う人も中にはいるかもしれませんが、
銀行金利ではありえなくても、
たとえば先週金曜日のダウ平均の終値は44,303.
3年前の1月の終値は35,131.
また、アメリカの名目GDPは、2021年の約23.
2024年の約29.17兆ドルへと増加しました。これは約1.
名目GDPで見ると7%、ダウ平均で見ると8%
日本を例に出せなかったのは、お察しの通り、5%
経済が7%で成長するなら、人も同じぐらい成長したいものです。
でも、自分が対前年比で7%伸びる、5年後には1.
どのような状態なのでしょうか?
また、どうすると、そうなるのでしょうか?
私は、「経験知識資産」と「思考資産」
成長と捉え、投資のイメージで捉えてみました。
「経験知識資産」というのは、
これまでの経験を通じて得た知識の総量です。
経験A1が、経験A2になった場合は、
経験Aを経て、Bを経験した場合は、
これらを合わせて、去年より7%
ということは、
まったく違うことを経験すると仮定したら、
7%の時間を新しいことに使う必要があります。
具体的には、1カ月の就労時間で見てみると、
月160時間×7%=月11.2時間、
こんな取り組みをすると、7%
もう一方の「思考資産」はこんなイメージです。
たとえば、1つのタスクに対して、
取り組む前の想像や予測、取り組み後の考察を、「3つ」
この人が、このタスクに対して7%思考を増やしても、
「3」が「3.2」になるだけで、
しかし、人間の脳は1日に1.
こうするだけで、1日の総量はもとより、
「3」を「3.2」にすれば良いなら、できそうに思えてきます。
「経験知識」と「思考」以外にも成長材料はあるかもしれません。
最初、「人脈」という発想もありかな?と思ったのですが、
人との関係を投資に見立てるというのも、
なんだか見返りを期待しているようでも、セルフ却下しました。
さて、自分の成長を数字でイメージしてみるという人体実験、
成功しましたか?
私は、頭を動かしてみて、
2月は早いです。
寒さに負けずにグングン行っちゃいましょう!
「ポジティブ VS ネガティブ」論
車のラジオを聴いていたら、ゲストにアンミカさんが出てきて、
彼女監修の「ポジティブ手帳2025」
ああ、もう手帳が話題の季節なんだな...
その手帳には、週次でポジティブワードが紹介されていたり、
心と体を元気にするハウツーが書いてあったりするらしいです。
手帳の内容自体は真っ当で良いものに思えました。
でも、一抹の違和感があって、何だろう?と考えてみたので、
シェアさせてください。
まず、ネーミング。「ポジティブ手帳」...。
Positiveは、積極的、前向き、
ポジティブな姿勢、ポジティブな考え方、
どう転んだって、良いことに違いありません。
しかし、私には、若干「煽り」
多分「ポジティブ」
社会では鬱などに悩まされている人が増え、
経済環境も良いとはいえないので生きにくい時代です。
夏目漱石ではありませんが、
だからこそ、この「ポジティブ」
そう、先導であって、扇動ではないのかもしれませんね。
でも、本当に心が豊かで健康的な状態というのは、
ポジティブであろうと努力することではないと思います。
たとえば、ネガティブ・ケイパビリティという言葉があります。
どうにも答えの出ない、どっちつかずの状況にあっても、
その不安定な状態、懐疑的な気持ちや違和感を抱えた状態に
留まって耐える力を意味します。
決してポジティブであろうと努力するのとは違います。
それは、
なので、ネガティブ感情から抜け出したいがために、
ポジティブであろうとすることは、
自分にとっては偽りの状態なので、健康的ではないと思うのです。
ネガティブな自分に気づいたら、それも素直に受け入れて留まる。
一番良くないのは、
というわでけ、ポジティブであろうなどと意識せずに、
普通に暮らしていて満ち足りているのが一番なのではないか、
その状態に呼び名はないのだろうか?...と思って調べてみたら、
「中庸」(ちゅうよう)と呼ぶらしいです。
この概念はギリシャ哲学や
中国の自然哲学「陰陽道」(おんみょうどう)から生まれ、
日本文化は後者から影響を受けています。
NHK大河ドラマ「光る君へ」に、ユースケ・
陰陽師・安倍晴明公が登場していました。
彼が礎にしていた思想が陰陽道です。
いったい「陰陽道」とは何でしょうか?
天地の間には、互いに対立し依存し合いながら、
万物を形成している陰・陽の2種類の気があるとされています。
積極的なものを陽、消極的なものを陰と呼びますが、
陰と陽には、善悪も優劣もありません。
「中庸」というのは、陰にも陽にも偏りすぎず、
何事においても過不足がなく、
勝手な解釈ですが、そうであるなら、
ちょっとしたポジティブは中庸にとって普通のこと。
そんな中庸の状態が私は健康的だと思います。
努力しなくても、
あ、でもポジティブ手帳を買うことで、
良い1年を送れそうな気がするならそれもアリですよね。
自分をコントロールできるのは自分だけですから。
いよいよ11月に入ってしまいました。
中庸な1カ月にしたいものですね(笑
「自分を生かせる」って?

当社は、現在、採用活動を行っています。
私は、採用/求職活動の本質は「その人を/自分を生かせるか」
企業と求職者の双方が見極めることだと思っています。
では、仕事で「自分を生かせる」
まず、「自分を生かせるか?」
「自分に合っているか?」というものがあります。
合っていれば、生かせる確率は高いですよね?
では、いったい何が「合っている」必要があるのでしょうか?
やりたいことか? 適性か? 価値観か?
他にもいろいろあると思いますし、どれも重要なのですが、
上の3つで言えば、価値観、適性、
なぜ、「価値観」が第一なのかといえば、
価値観というのは「自分らしくいられるか」の尺度だからです。
つまり、人の幸福と密接に繋がっています。
価値観には正しいも正しくないもありません。
自分はずーっとこれこれを大切だと思ってきた、
それと違うことをするのは抵抗がある、という類のことです。
たとえば、
「入社したての君が意見を言うのは十年早い」
という価値観の会社に入ってしまったら、これは不幸ですよね。
反対もまた然りで、
明快な意見などないし、
「年齢社歴に関係なく、当社社員なら意見を持っていてください」
という価値観の会社にいたら、これも苦痛に違いありません。
価値観が合わない会社に勤めるということは、
自分らしくないことを求められるということです。
でも、いざ自分の価値観を言語化しようと思っても、
実際にやってみると結構難しいです。
自分の価値観を知る上で、手っ取り早い方法は、
不快なこと、嫌いなこと、カッコ悪いと思うことを洗い出すこと。
自分と、人や仕事とのマッチングを考えるときに有効ですよ。
「合っている」において、その次に重要なのが「適性」です。
価値観が合っていたとしても、適性がないと、
とてつもない努力をしないといけなくなる。
苦手なことをがんばるよりも、
得意なことなら努力とも思わずにやり抜くことができます。
「自分に合っている」ためには「やりたいことかどうか」も、
もちろん重要ですが、これは案外「思い込み」
どういうことかといえば、やったことがないことを「やりたい」
やってみたら、
反対に、やりたいと思っていなかったことでも、
やりたいことに変化する場合もあります。
だから、やりたいことかどうかというのは、
さて、自分に「合っている」の話をしてきましたが、本題は「
端的に言うのは難しいですねぇ。
ここでは、「合っている」が満たせた上で、
自分の実力より少し上で、工夫の余地のある環境で働くこと、
と定義してみました。
どんなに周囲から喜ばれたとしても、
自分を生かしているとは感じにくい気がするからです。
「少し難しい」けれど、でも「できる」という仕事において、
自分なりの工夫の余地がある。
そんな環境で働くと、人は意味を感じるのではないでしょうか。
あなたは、どう思いますか?
自分を生かせているか?
より良い人生を送るために、時々考えたい問いです。
今年もあと3カ月。2024年の第3コーナーですね。
最後まで元気に走り切りましょう!
戦略家がやっているらしい「予測」の話
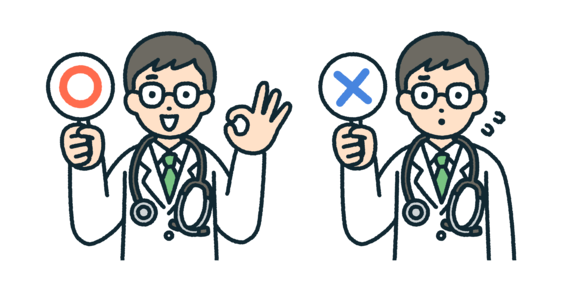
地震や台風などの天災、パンデミック、急にやってきた米不足...。
経済や国際情勢を含め、
予測しようもないからこそ、今日は「予測」
というのは、先週の木曜日、
左手を添えないと歯磨きさえできません。
そこから1週間、自分の行動を観察したり、
結局ここには「予測」
ご心配をお掛けしても申し訳ないので結論からお伝えすると、
当初はどうなるかと思った手首の症状も日に日に良くなり、
あと二、三日もすれば、元通りになっていると「予測」します!(
この間に私が取った行動は、木金土日は様子を見て、
月曜日に地元の脳神経外科へ行きました。
脳には異常はないが頚椎の可能性があるからと言われ、
大きな病院への紹介状をもらって翌日火曜日に整形外科に行きまし
結局、寝ている間に神経が圧迫されて起きたもので、
心配はないだろうという診断を得たので、
ゴルフも、筋トレも、ドラムもやるぞ~!
今回に限らず、発熱など緊急な場合を除き、
体調が悪くなったら、概ね1週間ぐらいで医療機関を訪ねます。
その理由は、宙ぶらりんだと予定が立たずに困ること、
最悪の状況ではないということの確証を得たいこと、でしょうか。
今回も楽観していましたが、楽観に基づいて行動すると
人に迷惑がかかる場合がある、というのもありました。
多分こういうことが、私の「予測に対する価値観」なんですね。
自分の体調に関しては1週間ですが、
仕事への対処はどんなに遅くても24時間の意識でいます。
何事も「最悪の状況」を想定して行動したくなるのは、
経営者特有のサガかもしれません。
あれは30代の半ば、
「最悪の事態を想定しろ。
希望的観測を捨て、しかし希望を忘れるな」
確かに...と思ったことを今でも覚えています。
最悪の事態を想定することの良さは、
「別に死ぬわけじゃないな」
しかし、人の予測行動は十人十色。さまざまな性分の人がいます。
体調を例にすると、、、
健康管理に気をつけて、日々対策している人もいます。
そういう人の持ち物を聞くととても面白いです。
また、具合が悪くなっても、
がんの手術などの大事に至っても、
セカンドオピニオンをもらう人もいれば、もらわない人もいます。
理由も、もちろんさまざま。
ある人は楽観的だからで、ある人は面倒だからであったり。
仕事でも同じように行動は分かれますよね。
人のことはともかく、私は「最悪の事態想定派」です。
悪い方から可能性を潰して、現実的な対応を考えたいタイプです。
ところで、OODA Loop(ウーダ・ループ)
私自身はこの原稿を書こうと思って、「予測」
今回初めて知りました。これが何かというと...
OODAループとは、アメリカの軍事戦略家であるジョン・
先の読めない状況で成果を出すための意思決定方法です。
現在では、
ボイドは、空中戦での決定的な勝因は、
意思決定プロセスを分かりやすく理論化しました。
Observe:観察する
↓
Orient: 状況を判断する
↓
Decide:意思決定する
↓
Act:行動する
PDCAが計画に対する業務改善モデルであるのに対し、
OODAは、迅速な意思決定を行うためのモデルで、
両者はしばしば比較されます。
なるほど。。。。
「なるほど」とは思いますが、私は2つのOの間で行う、
「Imagine」(想像する)が実は最も重要なのではないか、
予測の本質とはImagineなのではないか、と考えています。
想像する。
相手のことを。
相手の周りにいる人のことを。
自分の行動の後に生まれる状況のことを。
今、何もしなかった場合のことを。
3日後のことを。
1カ月後、1年後、10年後のことを。
その後に状況判断ですよね!
OIODA(オイオダ)です笑 戦闘では使えないけど。
今週、当社のニュースをお知らせをします。
楽しみにお待ちください! ではまた




