『リコメンド』カテゴリの記事
「意が伝わる」で大切なのは「幹」
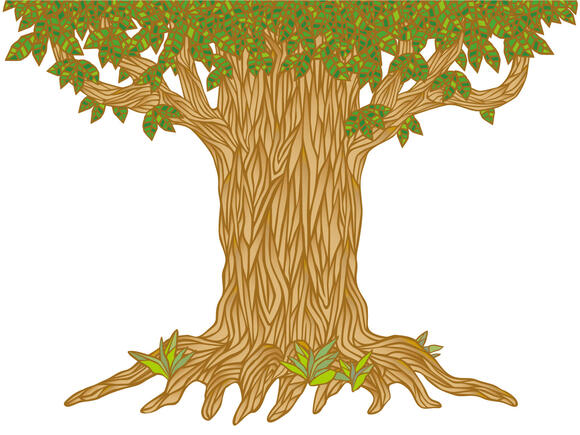
今日は、最近起きた3つの出来事を通じて思ったこと、
つまり表題にあるように、
ということについて私の脳内ぐるぐるをシェアさせてください。
自分のぐるぐるをそのまま吐き出すなーとも思いますが、
1つめの出来事です。
先週、私どものあるお客様企業の新社長になる方に
インタビューをさせていただく機会がありました。
その中で外部に自社の価値を伝えることがいかに大切かという話題
しかも、ただ説明すればいいわけではなく、
相手にとって「面白いか」「分かりやすいか」が重要で、
それが満たせると物事は自然と広まっていく。
インタビューの主題ではありませんでしたが、
また、2つめ、先週社内ではこのようなことがありました。
私が講師役となり「伝える技術」を学ぶ、
「テーマとは何か」を学ぶ課程では、
主題を端的に語ることの大切さを学んでもらうのですが、
「~について取り上げる」の「~」
簡単そうで簡単ではありません。
たとえば、「ABCプロジェクトについて」
「ABCプロジェクトの~について」
何に焦点を当てるかを言葉で表すとどうなるか。
やってみると、誰もが言葉を絞れずに悩むわけです。
「メッセージ」を言語化する場合にも同様なことが起きるので、
伝える人は、
この勉強会からの私の気づきは、
自分の考えの根幹を明確にしてから、相手に伝えるには、
自分の言葉を絞る必要があるわけですが、
それには理屈だけでは解決できず、
スポーツのようなトレーニングが必要なんだろうな、
さて、3つめ、最後のエピソードになります。
「伝わる」について考えさせられる出来事があった今週、
今度はなぜか不意に心が動いて、
なんと何十年かぶりに英語の学習教材を買いました。
基本はたった81文だというコンセプトで書かれた
「Simple English Magic 81」(著:酒井一郎)という本です。
きっかけは、この本を読むよりも前から、
若い時よりも英語が聞こえるようになっている気がする、
なぜだろうと考えてみると、
大体の大筋は何かと思って聞くと、想像力も手伝って、
こんなことを言っていると分かる。
昔は、聞き取れなかった単語が気になって、
私の自己分析を裏づけるかのように、
"I play baseball in the park next to the hospital."という一文を聞いた人の多くは、
"next to"に意識が向いてしまい、それよりも重要な"I play baseball"が
二の次になってしまう。
文意としては、そのようなことが紹介されていたのです。
つまり、人間が何かを理解したり、
幹が先であり、枝葉は後であるべきだということでしょう。
そしてまた、学習にも幹と枝葉があり、
滅多に使いもしないイディオムは枝葉、
幹は中学レベルで十分だということから、
つまり、相手に「意が伝わる」ようにするために大切なのは幹、
私が、テーマやメッセージを端的に絞れと教えているのも、
幹が先であり、枝葉は後だと思うからです。
3つの出来事を通じて、「伝える」「伝わる」
お付き合いいただき、ありがとうございました。
さて、当社、2週間後には通い慣れた表参道を離れ、大門/
引越し準備、大変でーす!
皆さんも期末でお忙しい方も多いと思いますが、
前年比7%増の自己成長って?

最近、ふとこんなことを考えました。
「年齢が上がると成長しにくい」は本当か?とか、
私自身の今の成長を数字で表したら、どうなるのだろう?と。
目標管理の世界では、目標はメジャラブル(測れるもの)
しばしば言われますが、目標と成長は別物です。
自分が対前年比で何パーセント成長したかなどと考えたり、
10年後には何倍に成長していたいなど、
数字で自分の成長を考える人は少ないのではないでしょうか。
また、いざイメージしてみようと思っても、
基準もないので、イメージできないという人が大半だと思います。
私自身は何歳になっても人は成長できると信じていますが、
キャリアが上がれば、新人の時のように
急成長を実感することはなくなるのが普通です。
というわけで、今日は「成長」を数字でイメージする、
チャレンジしてみたいと思います。
実験です笑、お付き合いください。
そこで、まず資産形成や社会経済を例に考えてみました。
たとえば、資産運用だとどうでしょう?
100万円を年利5%で運用すると、5年後に1.
年利6%で運用した場合は、7年後に1.5倍、10年後に1.
年利7%で運用すれば5年で1.4倍、
「今どき7%?」と思う人も中にはいるかもしれませんが、
銀行金利ではありえなくても、
たとえば先週金曜日のダウ平均の終値は44,303.
3年前の1月の終値は35,131.
また、アメリカの名目GDPは、2021年の約23.
2024年の約29.17兆ドルへと増加しました。これは約1.
名目GDPで見ると7%、ダウ平均で見ると8%
日本を例に出せなかったのは、お察しの通り、5%
経済が7%で成長するなら、人も同じぐらい成長したいものです。
でも、自分が対前年比で7%伸びる、5年後には1.
どのような状態なのでしょうか?
また、どうすると、そうなるのでしょうか?
私は、「経験知識資産」と「思考資産」
成長と捉え、投資のイメージで捉えてみました。
「経験知識資産」というのは、
これまでの経験を通じて得た知識の総量です。
経験A1が、経験A2になった場合は、
経験Aを経て、Bを経験した場合は、
これらを合わせて、去年より7%
ということは、
まったく違うことを経験すると仮定したら、
7%の時間を新しいことに使う必要があります。
具体的には、1カ月の就労時間で見てみると、
月160時間×7%=月11.2時間、
こんな取り組みをすると、7%
もう一方の「思考資産」はこんなイメージです。
たとえば、1つのタスクに対して、
取り組む前の想像や予測、取り組み後の考察を、「3つ」
この人が、このタスクに対して7%思考を増やしても、
「3」が「3.2」になるだけで、
しかし、人間の脳は1日に1.
こうするだけで、1日の総量はもとより、
「3」を「3.2」にすれば良いなら、できそうに思えてきます。
「経験知識」と「思考」以外にも成長材料はあるかもしれません。
最初、「人脈」という発想もありかな?と思ったのですが、
人との関係を投資に見立てるというのも、
なんだか見返りを期待しているようでも、セルフ却下しました。
さて、自分の成長を数字でイメージしてみるという人体実験、
成功しましたか?
私は、頭を動かしてみて、
2月は早いです。
寒さに負けずにグングン行っちゃいましょう!
「分解力」を磨く年に!

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ゆっくりお過ごしになれましたか?
私は、忙しいとなかなかできないこと、たとえば、
旅行のプランを立てたり、ケータイの乗り換え先を調べたり、
鍋を磨いてみたり、、、てなことをしていたら、
あっというまに休みが終わりました。
さて、今年の新年、いつも以上にワクワクするので、
なぜなのだろうと考えてみたのですが、
それは多分社会が大きく動く重要な年になる...
そんな気がするからなのだと思います。
良いことも悪いことも起きるでしょうが、
重たい扉が音を立てて開いていくようなイメージがあります。
社会の変化に関わっている要素はいろいろあるでしょうが、
AIの進展も重要要素の1つですよね。
AIを使うと何ができるのか、
どんな価値が生み出せるのかを考えるのは、とても楽しい。
まずは自社の業務をどう改善できるかを試しながら、
お客様に役立てることを考えていきたいと思います。
AIを使いこなそうと思ったときに何が必要になるのか?
私は「分解力」は欠かせないと感じます。
というのは、
インプットしてからアウトプットするまでに、
自分がいったい何をしているのかを明らかにし、
AIに学習させる必要があります。
たとえばメールを書くときに、
いったい何を、どの順番で考えて作文しているのか。
業務は暗黙知に溢れていますから、
根気がないとなかなか分解もできませんね。
でも、たとえば受験勉強とか、
習得の早い人は分解が上手な人なのではないでしょうか。
そうそう、昨日、散歩の途中で図書館が開いていたので、
目的もなくふらりと立ち寄りました。
私が立ち止まったコーナーは、旅行とスポーツです。
(文学でないところが私らしいかも笑)
で「ロジカルゴルフ」(尾林 弘太郎著)という本を手にとってみると、
ミスショットの原因を分解して捉えて対策が書かれていて、
改めて、やっぱり学習では分解というアプローチが大切だよなーと
実感した次第です。
同じようなことを東大受験支援の専門家である西岡壱誠さんも
東洋経済オンラインで書いています。
ただ英語ができないではなく、
「意味が複数ある単語を覚えられない」とか
「リスニングのときに毎回聞き取るスピードが遅くて困る」など、
分解されている悩みは解決策もわかりやすい、と。
反対に、問題がぼんやりしている人は、
まだ勉強を本格的に始めていない場合が多いのだそう。
私は楽観的なのか、業務を体系的に整理すれば、
AIを使いこなすことは簡単にできるのではないか、
実際には根気がないとできないことかもしれません。
ということは、「分解力」に加えて、
「ねばり力」も必要ということかもしれませんね。
仕事するって大変だな~
年の初めの「これをやりたい」という意欲を維持して、
良い1年にしていきたいものですね!
新年1号目を読んでいただき、ありがとうございました。
困る、悩むは「良いこと」

誰だって「悩みなんてない方がいい」、「安泰に暮らせる方がいい」、
そう思うのが普通なのではないでしょうか。私もそうです。
あ、今日のメルマガは新しいサービスとセミナーのご案内でもあるのですが、
ずっと考えてきたこととつながっているので、
回りくどいかもしれませんが、ちょっとお付き合いください。
「悩み」。
それは、精神的な苦痛や不安、負担を感じることを指すわけですから、
ない方がいいと思うのは、当然です。
悩みを解決する場合、大抵は現実を直視したり、
現状を踏まえて何かを変えなくてはならなかったりします。
なので、人間がいやだと感じるのは、悩み自体もあるでしょうけれど、
むしろ、それを直視して、何かを変えることの方なのかもしれません。
でも、人生、何事も意味づけによって、見え方が変わります。
悩みに良い面がないかというと、実はそうでもありません。
少なくても自分の人生を振り返ってみると、そう思います。
特にバブル崩壊やリーマンショックなど、激震と言えるような変化が起きると、
経営者としては安穏としてはいられませんでしたが、
今では「過去のあの出来事があって良かった、
当時は本当にキツかったけど...」と思えるようになっています。
どんなことが良かったかというと、
悩みの大きさとInput量は正比例の関係にあり、
悩む都度、答えを探してメチャメチャInputしたこと。
その結果、知識が増えて、それをサービスづくりにも生かすことができました。
こんなこともありました。
40代の初めの頃、社員から「うちの会社のミッションがわからない。
存在理由は何ですか?」と聞かれました。
自分は真面目に答えているつもりでも、どうやら答えになっていないらしい。
その時もたくさん本を読んだ記憶があります。
もし悩みがなかったら、多分、勉強しなかっただろうと思います。
まあ、いずれも苦し紛れですけど(笑、ストレッチだと思えば希望も湧いてきます。
だから、悩みには良い面があると思うわけです。
そんなふうに自社の悩みと向き合うことを繰り返すうちに、
うちの会社は、モヤモヤ嫌いの人が多く集まっていることにも気づきました。
モヤモヤをスルーせずに、大切に扱い、モヤモヤを解決することで、
晴れ晴れした状態にすることに意義を見出す人が多い。
人が分かり合うには、共有すべき考え方を整理し、クリアにする必要がありますが、
自分たちがモヤモヤと向き合ううちに、社会のモヤモヤ解決のお手伝をしたい、
コンセプトオーガナイザーという存在でありたい、と考えるようになりました。
今回のサービスが生まれたのも、そんな思いからです。
さて、、、、
新しいサービス名は、「トレジャーハント・プロジェクト」。宝探しです!
どんなものかというと、バリュー経営を支援するためのサービスです。
一般に、バリューという言葉は、「価値観」という意味で使われる場合と、
「提供価値」という意味で使われる場合がありますが、
ここでは「価値観」の意味で使っています。
価値観が曖昧ということは、行動基準が曖昧な状態のため、
行動がバラけて、組織はまとまりにくくなります。
つまり、自社の価値観を言語化して、社内で共有することによって、
組織の気持ちをひとつにするためのサービスです。
では、なぜ「価値観」が「宝物」(トレジャー)なのでしょうか?
どんな企業にも、大切にしたい価値観、《絶対譲れない価値観》があります。
たとえば、リスクとチャレンジへの価値観。
「石橋を叩いて渡れ」という企業は、リスク感覚が甘いと非難されることでしょう。
反対に、「やらないのは失敗と同じ」という企業では行動しないことがNGのはず。
しかも、リスクとチャレンジに対し特別なこだわりがなく、
ほかのことを重んじる企業もあります。
どれが正しいわけでもありません。ただ、価値観は企業文化の根幹にあり、
行動の源泉になっていることだけは間違いありません。
それは、個人も同じです。人は自分の価値観に従って行動します。
だから、組織と個人の価値観がどうしようもなく異なっていると、
幸せな結果にはなりません。
組織の価値観が明確になり、共感できていると、パワフルな状態になりますが、
往々にして価値観は暗黙知です。
言語化している企業もありますが、解釈自体は暗黙知の場合が少なくありません。
つまり、その企業の《絶対譲れない価値観》は、宝物として社内に眠っている、
それを明らかにして言語化しよう! そんな意図からこのサービス名になりました。
組織がまとまらなくて悩んでいる企業経営者の方へ、
このメッセージが届きますように。
こちらのURLで「バリューセミナー」のご案内をしています。
http://www.grassroots.co.jp/LP/internal-power/
少人数で開催しますので、ご興味がありましたら、お早めに。
では、今週も素敵な1週間をお過ごしください。
メモを取るのは何のため?
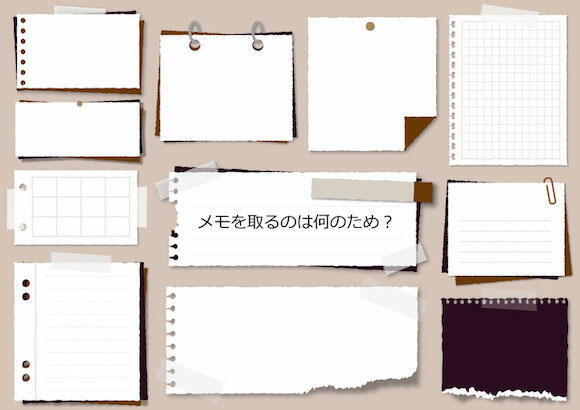
実は最近、本当は別の調べものをしていたのに、あちこちのサイトを巡るうち、
「メモの取り方」に関し、二人の人物が同じような意見を発しているのを目にしました。
それは、「メモを取る目的」についてです。
私自身あまり深く考えたことはなかったので、
シェアさせてください。
私が注目した二人というのは、
メンタリストDaiGoさんと、SHOWROOMの社長である前田裕二さんです。
前田さんは、2018年に「メモの魔力」(幻冬舎)という本を、
DaiGoさんは、2019年に「人生を変える記録の力」(実務教育出版)という
本を執筆しています。
私は、これらの書籍を読んでいませんが、
本の内容に関するインタビュー記事やYoutubeを見てみると、
前田さんは、「知的生産を目的にしたメモ」
DaiGoさんは、「創造につながるノート」
というような表現で、メモを取ることの目的を語っています。
メモの語源は「memorandum」(備忘録)であるように、
情報を記録するという目的でメモを取る人が多いのではないでしょうか。
ですから、多くの人がメモと聞いて思い浮かべるのは、
話を聞いたり、何かをインプットするシーン...なのかもしれません。
でも、二人のメモの捉え方はそうではありません。
何かを生み出すためには考えることが必要で、
そのためにメモをする...と捉えています。
私自身は、記録するという意味でのメモの活用はもちろんしていますが、
記録という視点でのメモ取りは、決して上手ではありません。
一方で、何かを生み出し、何かについて考えを深めるために、
自分たちの思考を言語化したり、
概念を図解化したりすることは日常的に行っています。
私の感覚では、メモしているというよりも、
書きながら整理しているという感覚なのですが、
これ、偶然にも前田さんのやっていることと、とても似ていました。
前田さんがメモを取る上で重視している思考フローは、
3つの段階に分かれています。
1. ファクトを正しく知る
2. 抽象化する
3. アクションに転用する
それによってファクト(事実)がアイデアに変わるといいます。
「アクションに転用する」という表現は前田さん特有のものですが、
私流の表現で言えば、ほかのことにも「応用できるようにする」ということです。
ですが、今日、取り上げたい1番のポイントはそこではなく、
「抽象化」というアプローチについてです。
抽象化とは、ある一つの体験を通して、そこから何が言えるのか、
自分なりの教訓を導き出すことと言い換えてもいいかもしれません。
ところが、この「抽象化」というアプローチ、
ひと手間あるので、結構面倒でもあります。
似たような結果と原因の例を洗い出してみて、
それらの共通点を探り出し、パターンを見つけ出す。
こんなことを根気よく考え続けるわけです。
この作業を興味があるからという理由で続けられるというのは、
言ってみれば、かなりのオタクです。
何オタクかといえば、「思考整理オタク」。
かくいう私も、その一翼を担っているのかも(笑)
しかも、自分一人の頭の中が整理できたからといって、
そこに価値はなく、関係者の頭の中を、
合意形成しながら一緒に整理できて初めて価値になります。
なので、私の中で最も有効なメモ帳は「ホワイトボード」です。
さて、前田さんやDaiGoさんの、創造的であるためのメモという話、
どう思いましたか?
何かを創造しようとしたら、その前段階として、
インプット内容を書いて整理するということは不可欠だといえそうですが、
無駄な作業に思えて必要ないと考えてしまう人や、
抽象的な概念で話されることが苦手という人もいます。
そのような相手にメモする大切さをどう伝えるかは、工夫が必要ですね。
考えを整理し、創造するためにメモを作る。
このプロセスをあなたはどう考えましたか?
9月に入ったと思ったら、もう後半。
やりたいことをやり切ったと思える秋にしたいですねー
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください!
AIの時代だから持ちたい鳥の目
 今日のテーマは鳥の目「俯瞰力」です。
今日のテーマは鳥の目「俯瞰力」です。
年が明け、あっという間に1カ月半が過ぎようとしています。
実は、正月休みは「AI」をテーマにインプットしていました。
その結果、感じたのは、当社の仕事にもAIが関わってくるであろう、
ということでした。
たとえば、私たちの仕事では「文章を書く」ことが多々あります。
文章生成ツールはもう存在していますし、
ある法則で文章をまとめるなどはAIの得意とするところです。
AIの影響を良くも悪くも受けるのは、10年後ぐらいかなと思っていましたが、
5年後ぐらいに迫っている、そういう感覚を抱きました。
人がAIと違う存在感を発揮するには、
どんな力があるといいのか、考える良い機会になりました。
あなたは、ご自分の仕事とAIの関係、どう見ていますか?
ここから先は素人の私の考えです。真に受けないでくださいね。
ネットで検索するとわかりますが、現時点でAIがあまり得意でないことのひとつに、
「意味の解釈」というのがあります。
「言葉の解釈」「事実の解釈」「態度の解釈」などなど。。。
AIと違って、人は、同じ出来事に対して様々な解釈をします。
たとえば、お客様とのミーティングに当社から2名で参加していたとして、
終わった時の解釈が異なっているということが時々起こります。
だからこそ、2名で参加することに意味があるわけです。
銘々のメンバーがそこで話された内容について、
辞書的意味はわかっていますが、
そこでの言葉に託された言外の意味について、
各自各様の解釈をしていることは少なくありません。
たとえば「チームワーク」という言葉があります。
「チームワークを大切に」と言われたら、
何を意味していると思いますか?
チームの「和」? 「結束力」?
「協力」?「責任遂行」でしょうか?
私たちはこんなふうに曖昧な解釈に基づいて、
コミュニケーションを取っています。
曖昧な解釈でも問題が起きない場合もあれば、
とても重要な点で解釈を間違えていたために、
大きな問題になる場合もあります。
では、そもそも解釈とは何をすることでしょう?
私なりの言葉で表現してみました。
まず、誰かの言葉や態度を解釈するのであれば、
発した人の意図や背景、真意を汲み取ること。
事実や出来事を解釈するのであれば、
その周辺の情報や状況、関係者の思いなど様々なことを踏まえて、
その事実に対し意味づけをすること。
...なのかな?
さて、、、
誰かの言葉や態度を解釈する場合、
そこには正解/不正解があります。
正解を知っているのは、言葉を発したその相手ですよね。
一方、事実や出来事を解釈する場合は、
正解/不正解はなく、
利の多い解釈か、利の少ない解釈かがあります。
たとえば、有意義な気づきや学びのある解釈、
その出来事を巡る関係者の気持ちに近づけた解釈、
自分や関係者の気持ちがポジティブになれる解釈などは、
利のある解釈だと言えるかもしれません。
このように、正解はあったり、なかったりしますが、
どう解釈するかによって、その解釈の効力には違いがあるのではないでしょうか。
幅広い解釈の中から、効力の高い解釈を選択するために不可欠なのが、
1行目に書いた「俯瞰力」ではないかと思います。
「俯瞰して見る力」
要するに、物を見る視点をたくさん持っていて、
いろいろなアングルから全体を見渡して考える力です。
「〜という視点からこれを見ると、〜と解釈できる」を
なるべくたくさん考えられる人が、俯瞰力がある人なのだと思います。
だとしたら、ある事に対して、自分が1つの見方をしたときに、
他の見方はないかなと疑ってみることが大切なのかもしれませんね。
あなたは、ご自分の仕事とAIの関係、どう見ていますか?
どうぞ素敵な1週間をお過ごしください!
「継続」を求めすぎない
このブログは、2007年7月に始めたので、もう12年以上続けています。
メルマガを継続的に開始したのは、2013年7月。こちらも6年が経ちました。
メルマガの平均開封率は25%強と驚異的。もしよろしければ、登録してみてください!
この二つは、ある程度、覚悟をもって始めたので、
だから続いているのだと思います。
覚悟といっても、そのニュアンスはとても微妙です。
・原則「毎週」更新する。
・でもどうしても無理な時はパスもあり。
何が微妙かというと、どういう時にパスしていいか、
その線引きについては文言化していないからです。
結局は自分次第ということになります。
で、いったい私は何を基準に判断してきたのかを振り返ってみたのですが、
それはおそらく「継続性の担保」を基準にしてきたような気がします。
たとえば、毎週1回が原則なのに、2週に1回「今回は無理!」と判断してしまったら、
実質的には「毎週1回が達成できていない状況」になります。
でも、ほぼほぼ毎週1回書いていて、ああ、でも今週はどうしても無理...という場合、
毎週1回という継続性は担保されていると見なせます。
「継続性の担保」に明快なルールはありません。
結局、自分に対して何をOKするか、何をNGとするかに尽きます。
あ、でも今、これを書きながら、もう一つ重んじてきたことがあると気づきました。
「継続性の担保」の別の側面。
読者から見てではなく、自分が継続性を保とうという意識を持ち続けられるようにすること。
つまり、できているという感覚を保つための頻度はどの程度か、です。
それはやっぱり、「たまに休む」はOK、「時々休む」はナシ、と
本能的に思っている。
なぜなら、時々休むが定着すると、まず継続できないからです。
一方で、休むのは「罪悪」であると感じたら、これも苦しくて続かない。
その意識のバランスが継続に繋がってきたと思います。
さて、継続は力なりというように、継続はある面でとても重要です。
でも、それが好奇心のブレーキになってはいけませんよね。
先ほど、私は、ブログとメルマガについて、
「この二つは、ある程度、覚悟をもって始めた」と書きましたが、
何かを始める時に、いつもいつも同じようなスタンスかと言われると、
そんなことはありません。
たとえば、この半年の間に、人から見たら、
アレコレちょっと手を出しすぎでは?と思われるくらい、
いろんなことに手を出しています。
仕事のことは脇に置いておくとして、具体的には...
・ゴルフ
・俳句
・ドラム
・アウトドア
・寺社巡り
でも、これ、どれも興味があるから首を突っ込みたくなっただけです。
好奇心の赴くままにいたら、そうなった、という。
で、始めたらからといって、何かを極めなくたっていいし、
途中で飽きたらやめればいいと思っています。
始めるにあたって、継続できるかどうかなどまったく考えていません。
ここ、重要だと思うのです。
なんとなくですが、私たちの心の中に、何かを始めたら、やり抜かねばならん!とか、
軽い気持ちで始めてはいけないという思い込み、ありませんか?
私自身、10年前はそう思っていたかもしれません。
でも、年齢が上がって、人生は一度切りなんだから、そんな必要はないなと思いました。
継続はもちろんいいことだし、重要なことですが、
「継続できるかな?」という気持ちが起きて、
それを理由にセーブしてしまうのはもったいないですよね。
セーブしないとこんなことが起きます。
実は、私、つい数カ月前まで、「山登り」に憧れていました。
そして、実際に山に詳しい友人に連れられて、初心者コースに登ってみたのですが、
やってみて、自分はこれをやりたいわけではなかった...。
そうわかったのです。すごく重要な気づきでした。
一方、俳句はまだ初めてから2カ月ですが、
これは一生やっていきたいなと思い始めています。
なぜなら単純に楽しいし、いつでもどこでもできるからです。
さて、、、
では、あなたは「気軽に」始めること、
「覚悟して」始めること、区別していますか?
仕事でない限り、覚悟して始める必要なんてないと思います。
人生は短いのだし、興味が湧いたら、気軽に始める心意気!
いいのではないでしょうか!?
8月になりました!
暑くてイヤだなという気持ちもありますが、
同じ夏でも2019年の夏は1回だけ。楽しみましょう!
ネガティブ・ケイパビリティ〜答えの出ない事態に耐える力
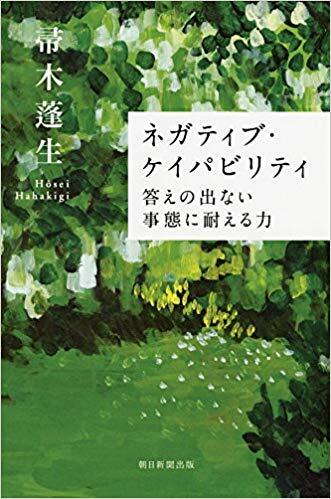
おすすめの本の話題です。
あなたは、物事に直面して、答えを出そうとする時、どんな気持ちが湧きますか?
あるいは、どんな気持ちが起きて、どんな葛藤をしますか?
私は、早く答えを出したいという気持ちと葛藤しながら、
焦らずにまずはきっちりインプットしようと自分に言い聞かせているような気がします。
「答えを出す」は言ってみればアウトプットなのですが、
いきなりアウトプットに向かってはいけないという感覚的な信念がありました。
でも、その時に湧いてくる気持ちは「早く答えを出したい」という気持ちです。
しかし、それではいかんと思ってきました。
でも、この感覚について人に説明するのは、結構難しかったです。
おそらくそれをやっても、大したレベルの答えが出ないと思っていたからだと思います。
そこを、うまく言語化してくれている本と出会いました。
「ネガティブ・ケイパビリティ〜答えの出ない事態に耐える力」(著:帚木蓬生、刊:朝日選書)です。
著者は小説家であり、精神科医です。
実は、まだ読み終わっていません。
でも、出だしの15%を読んで、これは自分が考えていたことを整理してくれる本だと、すぐにわかりました。
「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を指します。
私が、この考えに惹かれるのは、一般常識とはちょっと違ったことを言っているからです。
一般的に「能力」といえば、困った物事に対面した際に対処する能力...というイメージがあります。
そのこと自体には異論はないのですが、そう言ってしまうと、早い方が優れている、
そんなイメージになります。
でも、対処に至った考えの深さはどう考えるべきなのでしょう?
早く対処できた方が能力が高いのか、いや違うだろう?とそんな気持ちがありました。
精神科医が書いているだけあって、脳の話や医療の話なども出てきますが、
反対に小説家でもあるので、キーツやシェークスピア、紫式部の話なども書かれています。
今から読み進めるのがとても楽しみです。
ご興味があったら、ぜひ読んでみてください。
どこかで、もう少し深く、これについて一緒に考えて行きましょう。
少し暑くなってきましたね。
梅雨はいったいいつ明けるのでしょうか?
素敵な1週間をお過ごしください。
省力化したいなら、「考える」を省力化しない
グラスルーツは今年満35歳になりますが、
大分前から私が社員に向かって言い続けてきたことがあります。
それは、「自分で伸びていける力」を持っている人が強い、ということ。
言い換えば、一つの体験をした時に、
その経験を他に応用できるように吸収していける人が強いということです。
だから、私自身も、物事をマニュアル的に覚えるのは好きではありませんし、
マニュアル的に教えることも好きではありません。
ですが、マニュアルを作る発想で仕事をすることは、重要だと思っています。
微妙な表現ですが、これらは明確に違います。
マニュアル的に仕事を覚えるというのは、ただ「形」を覚えるだけになりがちですが、
その仕事の「本質」がわからないと良いマニュアルは作れません。
マニュアルを作る発想で仕事をすること、すなわち
本質的な視点で仕事を体得していくこと、
それが応用力を身につけるには不可欠なのではないでしょうか。
さて、これを読んでくださっているあなたご自身は、
応用力というものを意識したことがありますか?
私は、応用力があるのとないのとでは、人生がまったく変わると思います。
応用力がないと、どの体験も人生初体験になり、
毎度、「わからない」という不安な気持ちを味わうことになります。
でも、応用力があると、前にやったあの体験を応用すればできそうだ、
と思えるので、不安感が大幅に下がります。
ポジティブに言えば、自信を持って臨むことができます。
効率も生産性もまったく違います。
ということは、経済活動における自分自身の価値も変わってきます。
さて、その応用力というものを考えて行くときに必要だと思えてくるのが、
やっぱり、考えを深めるという日々のプロセスです。
考えることなくして、本質はわからない、
事柄の本質がわからないと応用はできないので、考えを深めるプロセスが重要です。
これは、1日1回あるというようなことではなく、1日何度も生じます。
つまり習慣化できるかどうかが鍵となっています。
ところが、世の中、考えを深めることが習慣でない人は多いと感じます。
当社でも、最初は慣れていない状態で入ってくる人が少なくありません。
入った会社にもよるかもしれませんが、社会人になると、考えることが求められ、
その結果、考えることに慣れて行く人もいれば、
なかなか徹底できず、習慣にならない人もいます。
でも、先ほどの話に立ち戻ると、
会社から求められるから考えることが必要なのではなく、
自分が過去の経験に基づいて応用力を効かせられるようになることが
不安をなくし、自分の成長に繋がるから、考える習慣が大切。
これが私の意見です。
私は、考えることに慣れていない人たちには、共通点があると思います。
特に重要なのは次の2つです。
(1)自分がわかっているのかどうか、見極めようとしていない。
(2)「自分で考えるよりも、教わる方が早い」と思っている。
この2点について、もう少し詳しく見て行きましょう。
ですが、これは、私の想像であって、断定する根拠は何もありません。
強いて言うなら、35年間の人間観察の結果でしょうか?笑
(1)自分がわかっているのかどうか、見極めようとしていない。
(ので、疑問が湧いてこない)
その理由はおそらく:
①「自分は今、本当に理解できているか」と自問する習慣がなく、
「感覚的にわかったつもり」で済ましているから。
自問する習慣がない理由はおそらく:
・「そんなことをしていたら、間に合わない」と焦っているから。
・「そこまで深く考えなくても、できるだろう」と思っているから。
そして、実際、価値の高さにこだわらなければ、そこまで深く考えなくても、
何かしらできてしまうので、その大切さに気づけない。
②仮に「自分は今、本当に理解できているか」と自問したとして、
何をもってわかったと言えるのか判断基準を考えることをしないので、判断できない。
判断できないことは、見極めようがないと思っている。
判断基準を考えられない理由はおそらく:
・目的思考で考える習慣がないから(目的から考えたら、わかるはずだが、そこに立ち戻る習慣がない)
(2)「自分で考えるよりも、教わる方が早い」と思っている。
一見早い面はありますが、疑問も持たずに教わろうとしたなら、
結果的には遅くなります。なぜなら伸びないからです。
こう考えてしまう理由はおそらく:
①わからない状態で考えた結果、間違えるなら、それはムダだと思っている。
②自分の今の力量で結論を出すのには時間が足りないので、精度の低い結論になる。
それは、非効率なので、教わった方が効率的だと思っている。
③実は焦りから、思考停止状態に陥っている。
...と、いろいろ書きましたが、
端的に言えば、「急がば回れ」と思えていないことが一因ではないでしょうか。
誰もが、できれば合理的で効率的に仕事をしたいと思っています。
それは間違いない。
しかし、考える習慣のない人は、省力化にこそ考えることが必要...
とわかっていないために、
考えることを省力化しようとして、結果的に非効率を招いているように見えます。
急がば回れなんですけどねぇ〜 ホントですよ、考えるスパイラルに入れれば、
あとは体験のすべてが貯金になるのですから。
また「考えるプロセス」を持つことが自分の仕事の価値につながる。
そこに、こだわるかどうかは、価値観の問題ですよね。
これは、むしろ生き方とか、美意識にも通じますので、
このブログで、私がどうこういうのは筋違いかな。
もちろん、グラスルーツの社員にはそうしたこだわりを持ってほしいですけどね。
長くなりました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
7月も後半。夏風邪に気をつけて、良い1週間を!
今を生きるために何を手放す?
今日は、一つのビデオ(上)を紹介します。
O&Oアカデミー創設者プリタジさんのTEDでのスピーチです。
彼女の考えによれば、ストレスや苦しみの意識の中で、幸福を考えても限界があり、
美しい意識状態にあってこそ、幸福に到達できる...そんなプレゼンテーションです。
イェスミとノーミ、二人の登場人物による物語を通じて、
そのメッセージを伝えています。
イェスミとノーミは、誰の中にもいるであろう心の動きを意味しています。
18分ほどの動画ですが、
聞けば聞くほど、あぁ、そうだなと思います。
ストレスの多い現代社会だからこそ、こうした考え方が必要だと感じました。
私たちはノーミになりやすい。
ノーミになっていることさえ気づかず、
自分を正当化する毎日を送っているのかもしれない。
そんな気づきを与えてくれます。
イェスミは、周りの目など気にせずに、自分の信じる通りの生き方をしています。
人にとってストレスになりうるネガティブな感情を超越して生きています。
本当にそれを実現することはたやすいとは思えませんが、
人のあり方としての理想のように思えました。
さて、話は関連するような、しないような。
個人的な話で恐縮ですが、昨日は母の一周忌でした。
命日は5月6日ですが、連休前にということもあって、昨日執り行いました。
母は、すい臓がんで余命宣告をされていましたが、
去年の今頃はすでに宣告よりもずいぶん長生きしていました。
4月初めはギリギリ寝たきりではなく、一緒にお花見をしました。
母はビール党で、大好きなスーパードライをまだ飲めていました。
そして、4月後半から食事もできなくなり、起きられなくなりましたが、
なぜか、母にも私にも悲壮感がなく、
亡くなったその瞬間にさえ一滴の悲しみもありませんでした。
むしろ、誇らしい気持ちで送り出した感じでした。
母の振る舞いや佇まいが私をそういう気持ちにさせたのだと思います。
今思えば、母がプリタジさんの物語のイェスミのように見えたのかもしれません。
何しろ85歳ですし、まだら認知ですから、
どこまで何がわかっていたのか、正確なところはわかりません。
でも、プリタジさんが言う「自分、自分、自分、、、」ということはなく、
自分の人生や過去に執着する様子もなく、
でも、今を大切にして「おいしいね」「きれいね」と言ったり、
施設のスタッフに「ありがとう」「悪いわね」と言ったり。
彼女にも人生に執着する時期はあったと思います。
いえ、ありました。
それなのに、どうしてあんなにあっさり手放せたのか。
もしかしたら、「2度目のがん」だったからかもしれません。
40代の終わりに乳がんになったとき、母はもっと人生に執着していたような。
そりゃそうですよね、しない方が不思議だから。
でも、85歳になって、何か達観したのでしょうか。
答えは謎です。
もしかしたら、ただ単に母を美化しているだけかもしれません。
でも、私にとってはある種の教材を母から与えられた心境です。
私は今を生きるために、いったい何を手放すべきなのか、
そんな問いが浮かんできました。即答できるものは何もありません。
あなたご自身はどうですか?
今週も素敵な1週間をお過ごしください。



